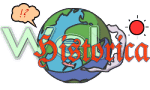WelHistorica
史学史(二)
最終更新:
welhistorica
-
view
| このページはウィキペディア日本語版の史学史 2006年9月14日 (木) 05:13 版を元にKanbunが改訂しています。 |
| 「史学史(二)」では、古文書学の成立から近代歴史学の展開までを対象とする。それ以前は「史学史(一)」を参照。それ以降は「史学史(三)」を参照。 |
歴史的展開
近代歴史学との関連性から、ここでは主に西ヨーロッパの歴史記述と記述方法論を中心に概観する。
| 「史学史(一)」から続く |
古文書学の成立
一方で歴史記述とは別個に、史料の批判的研究が着実な発展を遂げていた。それはいわゆる「古文書学?」で、ベネディクト派の学僧マビヨン?によって確立された。ただし古文書の真偽についてはマビヨン以前にすでに先行する研究があり、ここではその代表としてヴァラ?を紹介する[1]。
| [1]マビヨンに先行する組織的文献研究としては、17世紀のボランドゥス?を中心としたボランディスト?の古文書研究などがあげられる。(文献18:pp.102-103) |
ロレンツォ・ヴァラ
| ヴァラ 文献学的な研究に基づいて、『コンスタンティヌス帝の寄進状』を偽書だと断じた |
ヴァラは15世紀の人文主義者で、『偽イシドールス法令集』[1]中の『コンスタンティヌス帝の寄進状』という文書が偽作であることを明らかにした。この文書は中世を通じて、教皇領および教皇権に関する重要な典拠とされてきたので、教会は彼を宗教裁判にかけた。このことはこの時代、文書批判が既存の宗教や権威、慣習の批判につながっていたことを示している。事実、宗教改革?の時代になると、文書批判は急速に発展したが、それには新旧両派が文書を武器として互いの正統性を争うという背景があった[2]。
| [1] セヴィリアの司教イシドールス?の編とされる教皇法令集。9世紀に成立したとされている。 |
| [2]一方でこの時代に文書批判が進んだもう一つの理由として、古文書がかなり広汎に流出したことが指摘されている。ヘンリ8世?によっておこなわれた修道院?解散やドイツ農民戦争?およびシュマルカルデン戦争?、ユグノー戦争?、フロンドの乱?などの戦乱の影響で各地の修道院や教会に蓄えられていた古文書がかなり市場に放出されたという。(文献18:p.104) |
ジャン・マビヨン
17世紀フランスのベネディクト派?の一派サン・モール派に属する学僧であったマビヨンは、教団史や聖者伝などの編纂にあたるとともに、古文書の収集や刊行をおこなっていた。彼は1681年に『古文書論』[1]を著し、さまざまな文書を分類し定義づけた上で、インクや書体などを考察した。さらに言語がラテン語?やギリシャ語?などの古典語で書かれているか、それがどの程度まで古典的かなどの度合いで、その文書の時代性を明らかにできると述べた[2]。このことにより、さまざまな文書相互間の関係から客観的に文書の真偽を識別できる方法が確立され、古文書学が成立した[3]。
| [1]原題:De re diplomatica、1681年。 |
| [2]西ヨーロッパでは文書はラテン語で書かれるのが一般的であったが、中世になると地方の口語と接近し、「俗ラテン語?」と呼ばれる古典語よりくずれたラテン語が使われ、それらは今日のヨーロッパ言語のもととなった。俗ラテン語に対して、特にキケロ?に代表される典型的な古代のラテン語を「古典ラテン語」もしくは「古典語」という。今日一般的に言うラテン語とはこの古典語のことである。 |
| [3]マルク・ブロックは『歴史のための弁明』(原題:Apologie pour l'histoire)の中で古文書学の成立を歴史学における偉大な事業の一つに挙げている。(文献18:p.107) マビヨンに学んだイタリアのムラトリ?はこの時代の歴史学の学問的価値からいえば、後世から大変評価が高い人物で、ギボンは「イタリア史における我が師」と絶賛している。(文献18:pp.109-110、文献21:pp.39-40) ムラトリはライプニッツとも親交があったという。 |
近代歴史学の成立
 |
| ランケ 「特殊から一般へ」と述べて個別的歴史事実の重視を唱え、史料批判を方法論の中心に据えて近代歴史学を確立した |
一般に近代歴史学の成立はニーブール?とランケ?の研究を画期としていると考えられている。彼らの歴史研究の特徴は主に以下の3つである。
- 歴史事実の個別的把握
- 方法論としての史料批判
- 個別事実の一般化(世界史の形成)
これをいままで概観した近代以前の歴史研究の歴史に当てはめてみると、1.は啓蒙主義?の歴史学に、2.は古文書学に、3.はキリスト教?的な普遍史に求めることができる。この点で近代歴史学は近代以前の歴史学の総合として成り立っていた[1]。
| [1]近代歴史学を啓蒙主義・神学的普遍史・史料批判などの前近代的歴史研究の総合と見なす考え方は文献21:pp.36-37。ただし同書によれば近代歴史学の本質は史料批判という方法論におかれる。文献24:p.36も同様に史料批判を重視。 一方で文献18:pp.148-149では、史料批判ではなく歴史事実の個別的把握こそがランケの真骨頂であるとする。同書ではランケ史学はニーブールよりも当時の国際法学や政治学に影響を受けているという。 普遍史との関連性や宗教的背景を重視するのはマイネッケで、彼はランケの「個性原理」(歴史の個別的把握)を個体の中に固有の運動法則を認め、「一つの生」として歴史的個体を扱うことであるとした。そしてこれは汎神論よりも進んだ「万有在神論」と呼べる彼の宗教観に由来するものであるという。汎神論と万有在神論の相違は、汎神論には普遍的に神が存在するという意味で歴史事実の運動法則を普遍化しようとする傾向があるが、万有在神論は「万物に神が在る」という点から個々の歴史事実に固有の運動法則があるという認識に達する。したがって汎神論に基づく歴史記述では歴史的個体は埋没し一元的に普遍法則を設定していく過程になるのに対し、ランケでは固有の運動法則と普遍法則が論理的には解決されないまま並立しており、二元論的であるという。マイネッケはランケにマキャヴェリズムとの深刻な対立を見出しており、したがって一見道徳を排除しているように見えるランケ史学の深奥に道徳判断が認められるという。したがって彼の「個性原理」は国家行動をその研究の中心に据えながら、マキャヴェリズムに基づく近代政治学原理が歩んだような歴史的個体の普遍化・絶対化、つまり国家行動の全面的容認には至らなかったのだという。(文献22: pp.350-358) 継受の面が指摘される一方で、ランケでは前近代的歴史研究が持っていた実践主義的な観点や哲学的な視点は大幅に減じていることも認められる。(文献21:pp.45-47、文献24:p.38) 啓蒙主義と近代歴史学は以下の点で大きく対立している。 1. 啓蒙主義は一般から個別へと歴史を解釈したが、近代歴史学は個別から一般へと解釈した。 2. 啓蒙主義は古代の生活を近代においても空間的には存在しうるもの、たとえば非ヨーロッパ人の生活をヨーロッパ人の前文明的な生活と同質であると解釈することにより、歴史的事実を空間的に扱ったが、近代歴史学はそれを一回性の事実と考えることにより時間的に扱った。 ランケにおける個別的歴史事実の尊重と神学的普遍史との関連性については文献22:pp.348-368、啓蒙主義の歴史観については文献23:pp.68-74、文献18:p.122。 |
ニーブール
 |
| ニーブール ボーフォールの研究に影響されて、史料批判に基づいた実証的歴史研究をはじめ、ランケ以降の歴史学に影響を与えた |
ニーブールはボーフォールの伝承批判の精神を継受し、具体的な方法論としては複数の文献相互の整合性を検討する史料批判を用いて『ローマ史』[1]を記述した。このなかでニーブールは「海が流れをとりいれるように、ローマの歴史は、それ以前に地中海周辺の世界で名をあげられていた他の全ての諸民族の歴史を取り入れる」[2]と述べ、世界史のなかにローマ史を位置づけようとする試みが見られる。
| [1]原題:Römische Geschichte、1811年-1832年。 |
| [2]文献18:p.133による。同書ではランケも同様の言葉によって世界史の中でのローマ史の位置づけを語っていることも挙げられている。 |
ランケ
ランケはニーブールの『ローマ史』の方法論を近代史(彼から見て)の分野にも活かし、史料批判を通じて15・16世紀のヨーロッパ外交の構造から国家を個別的に把握する方法に考えついた。ランケは国家を一般化して考える啓蒙主義を批判して、国家を個別的に把握すべきと論じ、このような個別的歴史事実の相互関係から世界史を把握すべきことを提唱した。
近代歴史学の展開
 |
| ドロイゼン プロイセン学派の重鎮で19世紀後半のドイツ史学界に君臨した。元々は古代史を専門としており、彼の『ヘレニズムの歴史』によってヘレニズムという言葉の今日的な意味が定着したとされている。シュレスヴィヒ・ホルシュタイン問題など民族的な問題に強い関心を示した |
ランケの歴史研究はドイツにとどまらずヨーロッパ各国に衝撃を与えたが、ランケ以後の歴史学の性格はドイツとイギリス・フランスでは異なる方向へ進んだ。ドイツでは政治色の強いプロイセン学派?が台頭し、ランケの禁欲的な客観主義が批判されたが、イギリス・フランスではそれぞれ功利主義?や進化論?、実証主義?に影響されて、より科学的な方法論を追求する姿勢が現れた。 (詳細は近代の歴史学?を参照)
プロイセン学派
ドイツでは、1830年代の後半にダールマン?が登場し、国民主義?や自由主義?の風潮が高まった現実政治の影響を濃厚に受けた歴史叙述を著した。続くドロイゼン?とジーベル?も政治色の強い歴史研究を展開し、彼らは現実政治との関連性が著しいプロイセン学派を形成した。ダールマンとドロイゼンはともにフランクフルト国民議会?に選出された議員で、ジーベルもプロイセン議会の議員であった。プロイセン学派は当時のドイツ国民の熱烈な支持を受け、またドイツ国内の領邦君主とも利害が一致し、ドイツ史学界で支配的な影響力を持った[1]。彼らは個性の重視という意味ではランケを継承していたが、歴史事実の客観的把握と全く逆の視点に立つ歴史研究であったため、今日の歴史学の観点からすると、その評価は概して低く考えられている。
| [1]ドロイゼンは小ドイツ主義?を支持してプロイセン中心に民族的なドイツ統一が果たされるべきと主張した。ジーベルは神聖ローマ皇帝のイタリア政策についての論争(いわゆる「皇帝政策論争?」)の口火を切ったが、これも中世ドイツ皇帝権が普遍的であるか民族的であるかという主題の裏側に、小ドイツ主義と大ドイツ主義?のどちらが民族的統一としてふさわしいかという極めて政治的な背景があった。(文献18:pp.154-155) |
イギリスとフランス
 |
| バックル 統計学的手法を用い、帰納主義的な科学主義歴史学を展開した |
この時代のイギリスやフランスで主流となった功利主義・進化論・実証主義の共通する特徴は、内的要因よりも外的要因を重視することであった。具体的には、歴史を人間精神の創造的性格とか人間行動の主体的選択の結果として捉えるのではなく、自然的・物質的環境の影響に人間精神やその行動が、したがって歴史が規定されていると考えるものであった。この実証主義に立つ歴史学者の代表はフランスのテーヌ?とイギリスのバックル?である。特にバックルは統計学?を用いて自然環境や社会状況が歴史に決定的な影響を与えることを実証しようとした[1]。
| [1]この論争ではほぼ全ドイツの歴史家がランプレヒトと反対の立場を取り、またランプレヒトもあまりに歴史の法則性にこだわりすぎて、やや正当性に欠ける嫌いがあったので、結局はランプレヒトの不利なうちに決着したと考えられている。 |
「歴史の法則性」を巡って
ドイツ国内でも、歴史学の客観性を巡って歴史過程における法則性を研究の中心に据えようとする主張が現れた。すなわちランプレヒト?は、文化や社会などの類型的把握が可能なものこそ歴史考察において重要なものなのであるという主張した。彼の主張は史料批判に決定的に依存する当時の歴史学の持つ欠陥を適切にとらえたものであり、かつ個性を重視するそれと対立するものであったから、たちまち全ドイツ規模での論争に発展した[1]。
| [1]バックルに対しては、ドロイゼンが『歴史を科学の地位に高めること』を著し、倫理や個性の歴史形成における影響力を主張して反駁した。 |
「文化史」という視点
 |
| ブルクハルト 文化史の開拓者にして、すでに完成者としても十分な研究を残したブルクハルトだが、彼の生きた時代に対して独創的なその「文化史」は、直接的な後継者には恵まれず、独立的なものにとどまった |
史料批判に依存する個別的な歴史事実の把握に飽きたらず、より広い視野から歴史を総合的に把握しようという動きは「文化史?」の主張という形で現れた。「文化史」は、主に美術史の研究の手法を取り入れ、時代相互の文芸や美術、思想の様式的変化を総合的に比較して、それらの時代ごとの文化的特質を明らかにしようという歴史研究である[1]。この文化史の初期の代表的学者はスイスのブルクハルト?であり、彼の初期の著作『コンスタンティヌス大帝の時代』[2]において、すでに完成した形で「文化史」のスタイルが確立されていた[3]。前述したランプレヒトも文化史を中心に歴史を構成しようとしていた。
ランプレヒトの立場を批判的に継承し、文化史において画期的な業績をあげたのはオランダのホイジンガ?である。彼の代表作『中世の秋』[4]は生活・思想・文化などの諸相から14・15世紀のネーデルラントを複合的・重層的に描いた労作で、従来陰湿で否定的に捉えられてきた西洋中世の文化に「遊び」の精神を見出すものであった。この観点を発展させて遊びの形態とその表現を本格的に研究したのが『ホモ・ルーデンス』[5]で、この著作の視野は歴史学分野に限られず、文化人類学と相互関係にあり、その構想力の豊かさは優れて今日的な価値がある。
| [1]文化史の特徴としては従来の歴史研究が政治史を中心として縦断的に歴史事実を明らかにしようとしたのに対し、文化史は同時代のほかの事実および時代的な様式の特徴の関連性を重視して、横断的に歴史事実の背景を明らかにするものであったことが挙げられる。(文献25:pp.535-540) |
| [2]原題:Die Zeit Constantins des Großen、1853年。 |
| [3]今日的な視点で言うと、この著作はデータ的な面で時代遅れであるが、思想・社会・文化を一連の繋がりにおいて記述する、その歴史記述のスタイルは非常に意義深い。当時からこの著作はさまざまな欠陥を指摘されていたが、一時代を総合的に描いたその価値は一部で高く評価された。 |
| [4]原題:Herfsttij der Middeleeuwene、1819年。 |
| [5]原題:Homo ludens、1938年。 |
唯物論的歴史学
 |
| マルクス イギリス古典経済学、ドイツ観念論哲学、フランス実証主義などを批判的に総合して唯物論歴史学を打ち立てた。その歴史学は体系性に優れており、時代の要求に応えるものであった |
一方で歴史の体系的把握への試みは、当時近代歴史学と全く対立的な立場にあった哲学からも提示された。ランケの打ち立てた近代歴史学を痛烈に批判したのはヘーゲル?で、『歴史哲学』[1]において理論的関心に乏しい近代歴史学の風潮を批判し、普遍と特殊の総合に向かう理性的法則として歴史を認識すべきと説いた。彼の哲学は客観的な裏付けに乏しく、歴史学的要求に応えることはできないが、ランケがまた彼の歴史哲学をつねに批判の対象としながら、それに変わる体系性を用意することができなかったのも事実であった[2]。
このヘーゲルの歴史哲学を批判的に継承したマルクス?は、ヘーゲルが重視した精神に代わり、生産様式に注目した体系的な歴史哲学を打ち立てた。ヘーゲルの歴史哲学が極めて思弁的・精神的だったのに対し、マルクスは実証主義の外的要因を重視する姿勢を継承して、生産様式が人間の精神活動をも規制すると述べて、物質性を重視する唯物論?歴史学を唱えた。彼は古典経済学?の理論を批判的に継承し、労働を重視したが、労働の疎外によって支配階級による収奪が行われるとして、独自の階級理論を設定した。この階級理論をもとに発展段階的に歴史理論を構築し、時代ごとの生産様式の性格からその時代の文化様式にいたるまでの性格把握が可能であるとし、さらには未来史として階級が消滅した来るべき共産社会を予言した。
このようなマルクス主義?歴史学は従来の歴史学になかった優れた体系性を持つとともに、その理論的な堅牢性が高く評価された。歴史の体系的な把握を可能にした唯物論歴史学の登場は非常に画期的な出来事であったが、同時にこの歴史学は当初からさまざまな批判にさらされ、その理論の検証が着実になされていた。
| [1]原題:Gliederung und Zeitenfolge der Weltgeschichte、1830年。 |
| [2]ヘーゲルは事実の客観的把握というものには曖昧性が含まれており、かつどのように凡庸な歴史家でも自らの主観に従って能動的に歴史事実を選択し、それを通じて歴史を眺めているということを的確に指摘している。(文献21:pp.50-51) しかし彼の歴史哲学はその創造的性格のゆえに科学的ではなかったのであり、この点バックルら実証主義の歴史学のランケ批判のほうが正当であるというべきである。(文献21:pp.60-62) |
| 以降「史学史(三)」へ続く |
出典
※参照した文献は、その旨を記す際に煩雑さを避けるため、「文献」のあとに数字を示すこととする。具体的には「文献1」という場合は、下記のイブン・ハルドゥーンの『歴史序説(一)』を指すものとする。
- (文献1)イブン・ハルドゥーン?著、森本公誠?訳 『歴史序説(一)』岩波文庫、2001年
- (文献2)E・H・カー?著、清水幾太郎?訳 『歴史とは何か』岩波新書、1962年
- (文献3)蔀勇造?著 『世界史リブレット57 歴史意識の芽生えと歴史記述の始まり』山川出版社、2004年
- (文献4)田中美知太郎?著 『ロゴスとイデア』岩波書店、2003年
- (文献5)トゥーキューディデース著、久保正彰?訳 『戦史 上』岩波文庫、1966年
- (文献6)トゥーキューディデース著、久保正彰訳 『戦史 中』岩波文庫、1966年
- (文献7)堀米庸三?著 『歴史をみる眼』NHKブックス、1964年
- (文献8)村川堅太郎?編 『世界の名著5 ヘロドトス トゥキュディデス』中公バックス、1980年
- (文献9)溝口雄三?ほか編 『中国思想文化辞典』東京大学出版会、2001年
- (文献10)加藤常賢?監修 『中国思想史』東京大学出版会、1952年
- (文献11)宮崎市定?著 『史記を語る』岩波文庫、1996年
- (文献12)武田泰淳?著 『司馬遷 史記の世界』講談社文芸文庫、1997年
- (文献13)貝塚茂樹?著 『史記 中国古代の人びと』岩波新書、1963年
- (文献14)増田四郎?著 『大学でいかに学ぶか』講談社現代新書、1966年
- (文献15)金谷治?著 『中国思想を考える』中公新書、1993年
- (文献16)重澤俊郎?著 『周漢思想研究』大空社、1998年
- (文献17)顧頡剛?著、平山武夫?訳 『ある歴史家の生い立ち 古史辨自序』岩波文庫、1987年
- (文献18)中村治一?著 『史学概論』学陽書房、1974年
- (文献19)福田歓一?著 『政治学史』東京大学出版会、1985年
- (文献20)カッシーラー?著、中野好之?訳 『啓蒙主義の哲学 下』ちくま学芸文庫、2003年
- (文献21)林健太郎?著 『史学概論(新版)』有斐閣、1970年
- (文献22)林健太郎編 『世界の名著65 マイネッケ』中央バックス、1980年
- (文献23)弓削尚子?著 『世界史リブレット88 啓蒙の世紀と文明観』山川出版社、2004年
- (文献24)太田秀道?著『史学概論』学生社、1965年
- (文献25)ブルクハルト?著、新井靖一?訳 『コンスタンティヌス大帝の時代』筑摩書房、2003年
- (文献26)ハンナ・アレント?著、志水速雄?訳 『人間の条件』ちくま学芸文庫、1994年
- (文献27)アンリ・ピレンヌ?著、中村宏?ほか訳 『ヨーロッパ世界の誕生 マホメットとシャルルマーニュ』創文社、1960年
使用条件など
| この記事はGFDL文書です。 このページに掲載されている画像はウィキコモンズに公開されているものを使用しています。 |
-